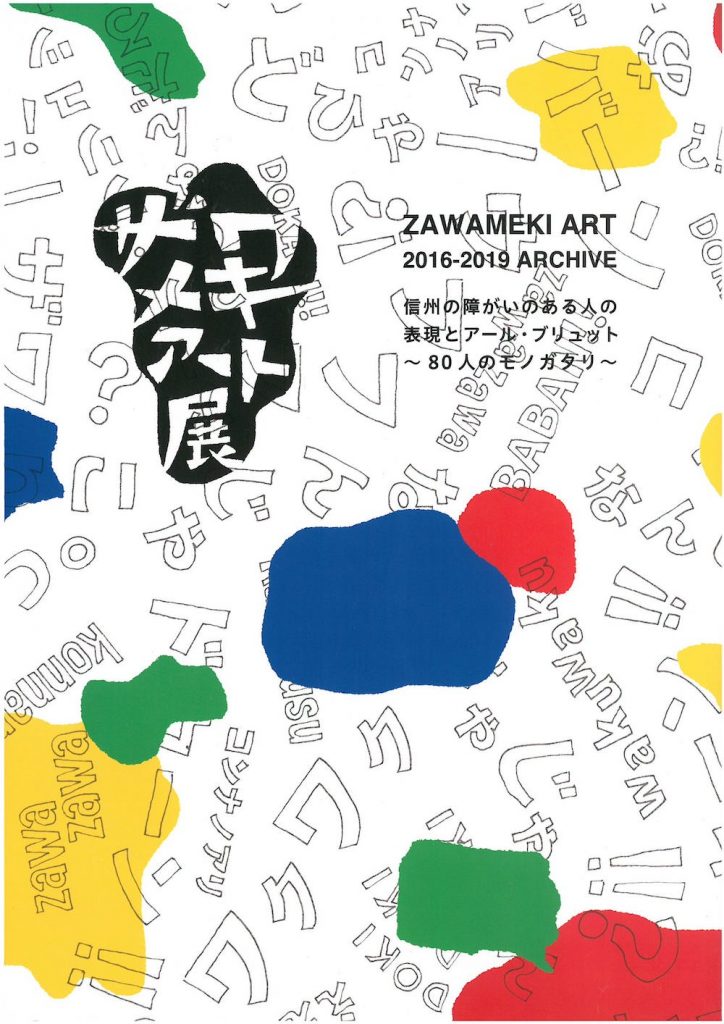「Light It Up Blue ちの 2019~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~」点灯カウントダウン(2019年4月2日~4月6日)
「Light It Up Blue ちの 2019~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~」点灯カウントダウン(2019年4月2日~4月6日)
茅野市民館は毎年、自主事業を検討するもととなる提案を、市民からアイデアとして募集しています。そうしたシステムを採用している文化施設は全国的に見てもまだまだ珍しいと言えるかもしれません。そんな中、ここ数年、福祉的な視点や、障がいのある人なども一緒に関われる企画の市民提案が増えています。地域の方々がそうしたアイデアを提案してみようと思う背景には何があるのか、茅野市民館と市民の関係には何があるのか、お聞きしたいと思いました。茅野市民館の指定管理者である株式会社地域文化創造の皆さんにお話を伺いました。
茅野市民館は茅野市美術館を併設し、劇場・音楽ホール、市民ギャラリー、図書室など多様な機能を集約させた文化複合施設として2005年にオープンしました。1999年からオープンするまでの6年間、市民主導で200回以上もの会議を重ね、管理運営計画をつくり、市民と協働での運営が行われています。
 「茅野市民館よりあい劇場 2018→2019 アイデア・パフォーマンス発表」(2018年5月12日)
「茅野市民館よりあい劇場 2018→2019 アイデア・パフォーマンス発表」(2018年5月12日)
茅野市民館は毎年、公演や展示といった催し物から日々の活動まで、地域の方々から事業についてのアイデア提案を募集します。さらに提案者によるプレゼンテーションを行い(写真上)、その内容や意見をもとに、市民を含む「事業企画会議」で事業案を検討するという過程を経ています。ここ数年、市民からの提案の中に、福祉的な視点や、障がいのある人なども一緒に関われる企画が見られるようになりました。私自身も「まぜこぜマルシェ」「障がい者芸術祭」など障がい者やマイノリティに関する企画を毎年提案させていただいています。そうした市民のいろいろなアイデアが組み込まれ、茅野市民館の事業が実現していきます。
近年の自主事業の中で「福祉」の要素を組み込んでいる取り組みをいくつか紹介します。
 茅野市民館みんなのひろば「パノラマ チノラマ」茅野の〈人〉と〈場所〉をめぐるツアー型パフォーマンス(2014年)
茅野市民館みんなのひろば「パノラマ チノラマ」茅野の〈人〉と〈場所〉をめぐるツアー型パフォーマンス(2014年)
 Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)
Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)ブルーライトアップ
 Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)
Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)アートワークショップ
 Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)
Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)リズムセッション
 Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)
Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)上映トーク
 Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)
Light It Up Blueちの~ひろがれ!青い光がつなげるこころ~(2016年~)啓発パネル展示
 ムジカ・タテシナvol.8小川典子ピアノ・リサイタル 関連企画「ジェイミーのコンサート」(2017年)
ムジカ・タテシナvol.8小川典子ピアノ・リサイタル 関連企画「ジェイミーのコンサート」(2017年)
 「ムジカ・タテシナvol.9 山崎祐介×山宮るり子ハープデュオ・リサイタル」関係者向けサロン「みんなで接遇研修」(2018年)
「ムジカ・タテシナvol.9 山崎祐介×山宮るり子ハープデュオ・リサイタル」関係者向けサロン「みんなで接遇研修」(2018年)
 茅野市民館をサポートしませんか2019ワークショップ「てとてで おはなし しよう」(2019年)
茅野市民館をサポートしませんか2019ワークショップ「てとてで おはなし しよう」(2019年)
 茅野市民館 みんなの劇場「はこ/BOXES じいちゃんのオルゴール♪」デフ・パペットシアター・ひとみ(2019年)
茅野市民館 みんなの劇場「はこ/BOXES じいちゃんのオルゴール♪」デフ・パペットシアター・ひとみ(2019年)
人とつながりたい、表現したいという欲求の開放&社会的なバリアを超えたうえで個々の命と関わる感性
「ここ数年、事業提案で福祉に関する事業が多くなったことや、まぜこぜ感を持つようになったきっかけをどう考えていらっしゃいますか?」
そんな質問を地域文化創造のスタッフの皆さんに投げかけてみました。
地域文化創造の前社長で、今年度より顧問に就任した辻野隆之さんから口火を切っていただきました。
「最初のきっかけは管理運営計画の中で、劇場や美術館を市民の手で創造していきましょう、世の中や業界の常識で“こうあるべきだ”と言われること、思われていることじゃないことをやっていきましょうという、ミッションがあるんですよ。ともになにかを体感する。ここでは、そうやって市民の皆さんがクリエイションして、地域文化を育んでいるんです。障がいがある方をはじめ、生きづらさを抱えている皆さんには日常に社会的なバリアがあるかもしれません。常識などといったもので閉じてしまった蓋を、ポジティブ・シンキングで開けること、それはアートの扉を開けることと似ている気がするんです。人とつながったり表現したいという欲求を開くことと、社会的なバリアを超えたうえで個々の命と関わる感性。アートをコアなところでやっていこうという姿勢と類似性があるんだと思います。理論的には説明できません(笑)。でもそれは、いわゆる芸術至上主義というか、アートが好きな人だけに閉じた環境では出てこない。アートって特別な人のものではなくて、みんなの心にあるもの。日常生活の中で、それぞれの持っているアートを愛でていこうよ、ということをやっていきたいんです」
 地域文化創造顧問の辻野隆之さん
地域文化創造顧問の辻野隆之さん
市民とともに管理運営計画をつくり、市民サポーターが生まれ、多くの市民が市民館の事業を支えています。オープン前から市民と共に体験しながらものづくりをしていこうという思いが今に続いているのです。
技術部長から社長に就任した久保祥剛さんは
「市民館と福祉に関することって、実は最初から内包されていたのかなと思うんです。普段から、障がいのある方がいる環境が当たり前だったんですよね。ワークショップの参加者に障がいのある方がいても、気にしながら見ていたりしますけど、講師の方たちも参加者の皆さんも普通にしていて、ボーダーがないんです。福祉や障がい者に関する企画が出てくるようになった理由は、そのことが基本にあるからかもしれません。僕、個人的にはボーダー的なことって昔から大嫌い。一番嫌いなのは国境です。なぜ国境を越えるのにわざわざパスポートを持って人に見せて通らなきゃいけないのか、今でもさっぱりわからない(笑)。そういう意味で、そこにあるものは、そこにあるものだとしか思えないのが僕の質としてあって、そこにいらっしゃる方がどういう方でも、その方とどう関われるかしかないんですよね」
と話してくれました。
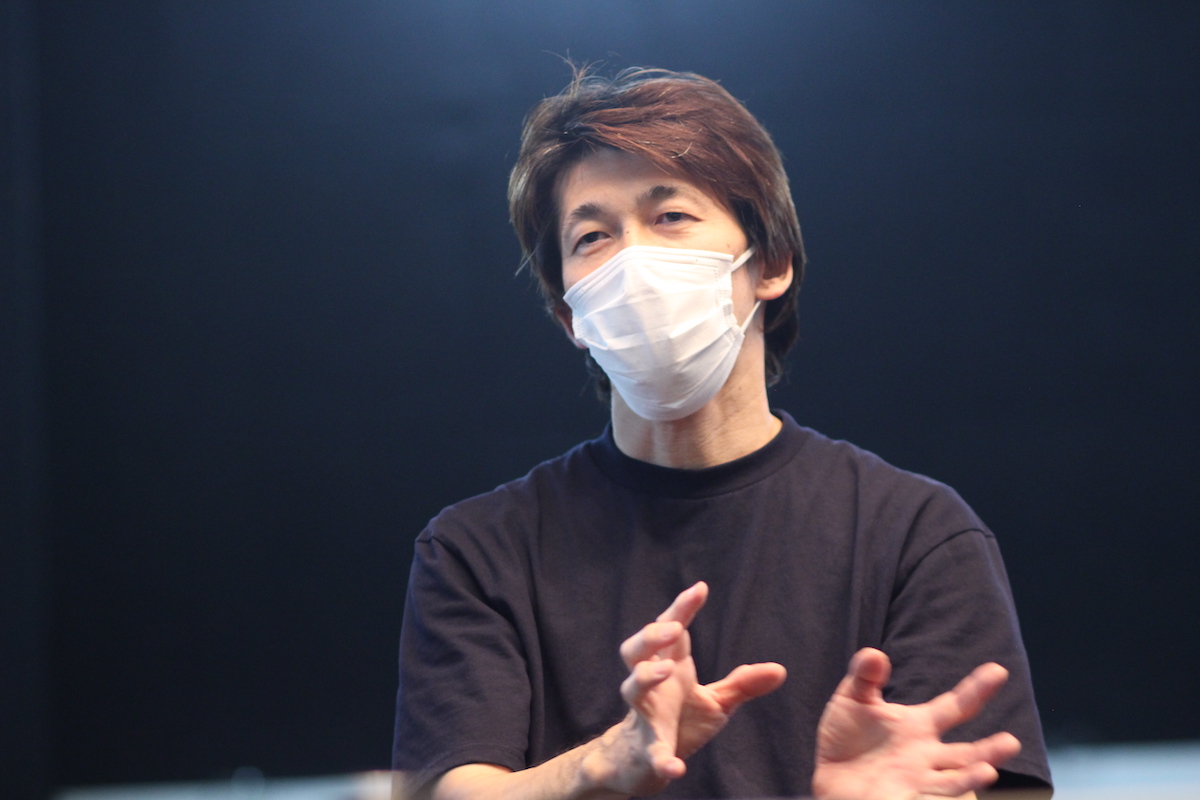 地域文化創造新社長の久保祥剛さん
地域文化創造新社長の久保祥剛さん
また、主任学芸員を経て美術館長になった前田忠史さんは
「美術館も劇場もハレの場であるというか、美術館だったら歴史的なものや現代美術的なうごめいているものを展示する、劇場でもそれに相当するいわゆる作品を上演するところ、というイメージが一般的にはありますよね。でも、開館3年目の2007年、ここに来たときにすごいな、と思ったのは、茅野市民館も茅野市美術館も、もちろん歴史とかアートのくくりの中のものを取り上げるけれども、一方で地域の皆さんの中にうごめいている衝動とか感じていることを拾い上げ、一緒に実現していく場でもあるということでした。市民の衝動を受け止め、見逃さずにつないできたというベースがある。当館の学芸員が、福祉とか障がいのある人に関することは常に光を当てていないと見えづらくなってしまうものだと言っていたのですが、だからそうした事業についても、そのベースをもとに必要に応じてネットワークをつないだり、フォローしてきたことが大きいのかもしれません」
と話してくれました。
 茅野市美術館新館長の前田忠史さん
茅野市美術館新館長の前田忠史さん
劇場、美術館両側から、それぞれの立場での市民館の基本的な考え方について話してくださったスタッフの皆さん。それに深くうなづいていた辻野顧問は続けます。
「今、前田美術館長が言ってくれたように、常にアンテナを張って、市民のアイデアを市民館がストーリーに入れ込むように持ってくる。でもそれに市民の皆さんが応えてくれないとムーブメントにはなりません。だから、両方ですよね。たとえば五味さんみたいな方たちが存在してきてくれたってことが大事で。打てど響かねば物語にならない。地域の中で活動されている方たちが、自分のこととして市民館という場を利用してくださるようになってきたのは、10年、15年くらいかかりました、最近のことですよ。でもその中からいろんなアイデアが提案されるようになってきたんです。『Light It Up Blue』(世界自閉症啓発デー)なんかも、まぜこぜの空気感があって、そこに地域で活動されている方たちが“市民館って受け取ってくれるかもしれない”って思い、遠慮しながら声をかけてくれた。そのときに寄り添う。それで、福祉の企画として構えるのではなく、七夕のような季節の催しと捉えることで、周囲にいる方も入ってきやすくなるじゃないですか。市民館は誰も排除しない、開いているよ、と意思表示しながら空気感を出していると、そういう人たちが“いいのかな”って来てくれる。そのときにパッと受け止める、寄り添うっていうスタンスを取るようにしているんです。その最初の印象、コンタクトはとても重要だと思っています」
確かに、誰もが自分の場として感じられる市民館だから、アイデアを受け取ってもらえるかもしれない、実現できるかもしれないという思いを持ち、それが事業提案につながっているように感じました。
提案者の中には、福祉に関わる仕事をされている方や、身近に障がいのある人がいるという方もいます。近年ノーマライゼーション(障がいの有無に関わらず平等に生活する社会を実現させる考え方)、ユニバーサル・デザインなどが提唱されるようになってきましたが、まだまだ福祉や障がいのある方が文化芸術に関われる機会はわずかです。だからこそ身近にいる方が、障がいのある人がアートを発信したり、鑑賞したり創造できる企画を茅野市民館でやれないだろうか、と望む思いは深いのでしょう。文化芸術活動を通した体験は自己肯定感を高め、心を豊かにしてくれるものなのです。
地元出身で、この地域でずっと暮らしてきた取締役総務部長の竹内陽子さんは、「私はここで働き始める以前はサービス業に経理で勤めていたのですが、市民館では本当にいろんな方が館を訪ねてやって来て、刺激的でありながら時には大変と思うこともあったんですよね。自分にとっては思ってもいない場に来ているというか、想定外でした。けれども、いろいろ経験を重ねていって、地域の皆さん、アーティストの皆さん、業者の皆さんなどと話していくとすごく楽しいなって。それぞれと共通言語ができてくると、その想定外もすごく楽しいなって思えるようになりました」と語ります。
 取締役総務部長の竹内陽子さん
取締役総務部長の竹内陽子さん
取材に同席した広報の後町有美さんに感想を聞きました。
「皆さんのお話を聞いていて、確かに福祉のこともそうですけど、やっぱり私たちはいろいろな方たちといろいろなことをしたいという思いがあるんです。それはもうスタッフも、市民のサポーターの方たちも。それこそ市民館は、建つ前からいろんな市民の方たちが意見をしてつくってきた土壌があります。そこに“一緒にやりましょう”というミッションがあって、それを普通のこととしてやっていける。“ここがすごくいいよね”と感じ合って一緒にやっていく、その積み重ねから“わたしもここにならこういうことが言えるかもしれない”“関わっているなかでこういうことに興味をもってきたよ”と言えるつながりが今、見えるようになってきているのかもしれないなって思います」
 広報の後町有美さん
広報の後町有美さん
茅野市民館は開館から16年間、市民と共に創造し、地域文化の拠点、交流の場となってきました。これからもますます、障がいのある方ない方、さまざまな皆さんが求める文化芸術への想いが集まる場であり続けてくれることを期待したいと思います。
取材・文:五味三恵
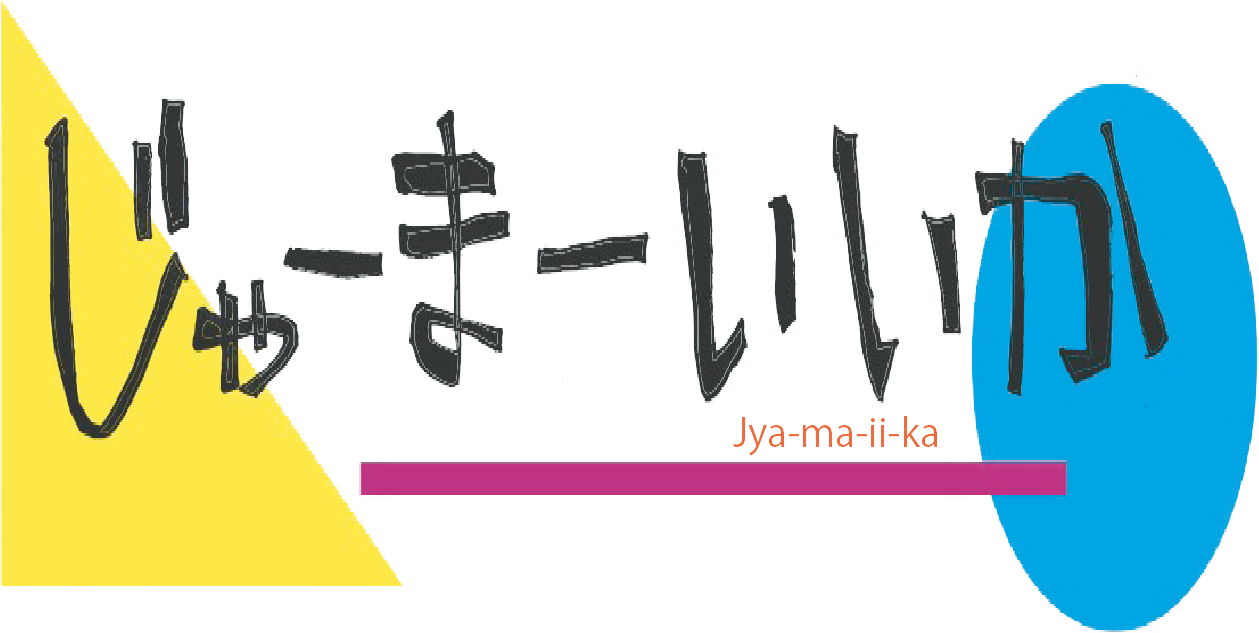

 監督をされた三好大輔さん
監督をされた三好大輔さん
 白鳥さんのお話を聞く川内さん ドキュメンタリー映画「白い鳥」より
白鳥さんのお話を聞く川内さん ドキュメンタリー映画「白い鳥」より
 川内さんも9月3日に白鳥さんとの美術鑑賞に関する書籍を上梓する
川内さんも9月3日に白鳥さんとの美術鑑賞に関する書籍を上梓する
 白鳥健二さん ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
白鳥健二さん ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
 写真:市川勝弘 ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
写真:市川勝弘 ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
 写真:市川勝弘 ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
写真:市川勝弘 ドキュメンタリー映画『白い鳥』より
 三好大輔さん
三好大輔さん
 三好さんは、その土地に眠っている8ミリフィルムなどのホームムービーを掘り起こし、市民とともに映画づくりの過程を共有し、新たな映画に仕立て上げる地産地消の映画づくりなども行なっている
三好さんは、その土地に眠っている8ミリフィルムなどのホームムービーを掘り起こし、市民とともに映画づくりの過程を共有し、新たな映画に仕立て上げる地産地消の映画づくりなども行なっている
![[対談] 櫛野展正さん(アウトサイダー・キュレーター、アーツカウンシルしずおかチーフプログラム・ディレクター)×稲葉俊郎さん(医師、医学博士)](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/08/ogp-1.png)
 櫛野展正さん
櫛野展正さん
 稲葉俊郎さん
稲葉俊郎さん
 「ヤンキー人類学」より
「ヤンキー人類学」より
 『アウトサイドで生きている』(タバブックス/2017)
『アウトサイドで生きている』(タバブックス/2017)
 スギノイチヲさんが扮装した「パブロ・ピカソ」
スギノイチヲさんが扮装した「パブロ・ピカソ」
 巨大生物が都市を破壊する危機を描く稲田泰樹さん
巨大生物が都市を破壊する危機を描く稲田泰樹さん
 「不動明王」の磨崖仏を掘り続ける田中唯支さん
「不動明王」の磨崖仏を掘り続ける田中唯支さん
 「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展」より
「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展」より
 創作仮面館
創作仮面館
 創作仮面館
創作仮面館
 櫛野展正さん
櫛野展正さん
 稲葉俊郎さん
稲葉俊郎さん
![[対談]ロジャー・マクドナルドさん×大谷典子さん](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/08/ogp2.png)