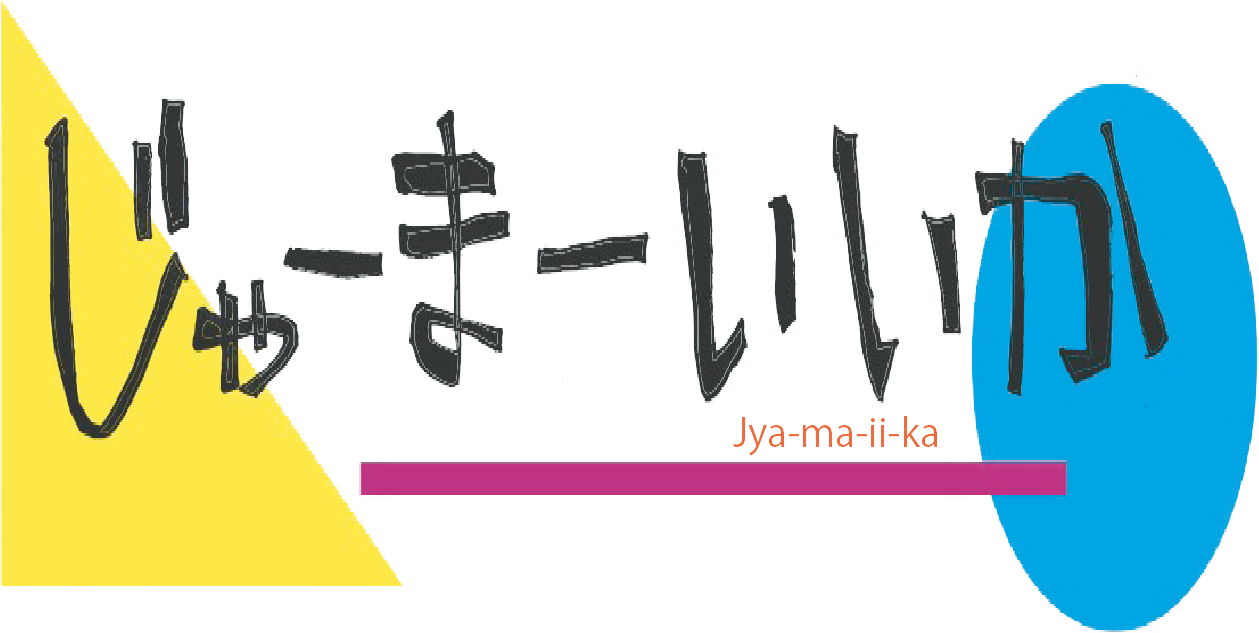[対談] 櫛野展正さん(アウトサイダー・キュレーター、アーツカウンシルしずおかチーフプログラム・ディレクター)×稲葉俊郎さん(医師、医学博士)
アートは身近なもの、誰もが表現の種を持っている
このサイトをつくろうと準備していたとき、櫛野展正さんのインタビューを読みました。展覧会のために障害ある人の作品を借りに行った櫛野さんは、作家のお父様から「君たちがお祭り騒ぎしているだけだろ」という言葉をぶつけられたと言います。もしかしたら『じゃーまーいいか』もそんなふうに見えるのかもしれません。だったらその言葉をサイト運営していくための戒めにしようと思い、櫛野さんに早い段階でご登場いただこうと思いました。対談相手に名乗りをあげてくださったのは、軽井沢在住の医師、稲葉俊郎さん。「文化芸術と医療はほぼ同じもの」と語る稲葉さんは実は櫛野さんの著書の愛読者でもありました。
 櫛野展正さん
櫛野展正さん
櫛野展正
日本唯一のアウトサイダー・キュレーター。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」でキュレーターを担当。2016年4月、アウトサイダー・アート専門のスペース「クシノテラス」を開設。既存の美術の物差しでは評価の定まらない表現を探し求め、全国各地の取材を続ける。主な展覧会に『櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展』(東京ドームシティ、2019)。近著に『アウトサイドで生きている』(タバブックス/2017)、『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』(イースト・プレス/2018)など。アートポータルサイト「美術手帖」にて『アウトサイドの隣人たち』を連載中。2021年より「アーツカウンシルしずおか」のチーフプログラム・ディレクターを務める。
 稲葉俊郎さん
稲葉俊郎さん
稲葉俊郎
医師、医学博士。2004年東京大学医学部医学科卒業、東京大学医学部付属病院循環器内科助教を経て、2020年4月より軽井沢病院総合診療科医長(2021年より副院長兼務)、信州大学社会基盤研究所特任准教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員、東北芸術工科大学客員教授を兼任。心臓を専門とし、在宅医療、山岳医療にも従事。西洋医学だけではなく伝統医療、補完代替医療、民間医療も広く修める。「山形ビエンナーレ2020」では現役医師として芸術監督を務め、医療と芸術の接点をテーマに「全体性を取り戻す芸術祭」として開催。単著『いのちを呼びさますもの』(アノニマ・スタジオ/2017)では、生命活動の発露の芸術としてア―ルブリュットにも触れている。近著に『からだとこころの健康学』(NHK出版/2019)、『いのちはのちのいのちへ』(アノニマ・スタジオ/2020)など。
高齢者を尊敬できる社会に
先ずは、櫛野さんから自己紹介をお願いします!
櫛野 生まれも育ちも広島県福山市で、2016年から「クシノテラス」というアートスペースを運営していました。もともと知的障害者福祉施設で職員をしていて、障害のある方々にアート活動の支援を始めたことから「鞆の津ミュージアム」というアール・ブリュットに特化した美術館を立ち上げ、そこで3年ほど死刑囚の絵画展やヤンキー文化をテーマにした展覧会などを企画していたんです。昨年末からは静岡県へ移住し、「アーツカウンシルしずおか」でチーフプログラム・ディレクターとして働いています。地域資源の活用や社会課題への対応を目指す先駆的なアートプロジェクトを公募し、活動経費の一部を助成するだけでなく、各団体に寄り添い、事業についてもサポートをする伴走支援が主な仕事です。僕が特に力を入れているのは高齢者の芸術活動です。「アーツカウンシルしずおか」では、ユニークな活動を続ける高齢者の方々の表現を『しずおか超老芸術』と呼び、取材を行うなどしています。今はアートスペースとしての「クシノテラス」の活動はお休みしていますが、全国各地への取材は続けており、未だ評価の定まっていない表現を生み出す人たちを見つけてはメディアで紹介しています。
 「ヤンキー人類学」より
「ヤンキー人類学」より
稲葉さん、お願いします。
稲葉 僕は熊本生まれですが、幼少期にはとっても身体が弱く、何度か死の淵をさまよった体験の記憶があります。そうした死の記憶により、ある時期から社会の見方が変わったようです。そして、医学や病院に助けられたという強い思いから恩返しを兼ねて医者になりました。東大病院では心臓の急性期治療に長く携わりながら、診療、研究、教育と、多忙を極めた日々を送っていたのですが、2011年の東日本大震災のときに福島へ医療ボランティアに行き、医療の原点や医師を志した最初の動機を考え直すきっかけになりました。ふと立ち止まり本当に自分がやりたいことを考え直すきっかけになったんです。自分がやるべきことを考え続けながら日々を送り、今のまま仕事を続けていても本当に自分がやりたいことは実現できないという結論に達しまして、2020年に家族で軽井沢に引っ越しました。今は軽井沢病院に勤務しながら町全体を医療の場にできないか、町全体を「屋根のない病院」にできないかと思い、医療の活動と町の行政とをリンクさせながら活動しています。僕がやりたいと思うことは、バラバラになったことで不具合が起きた領域をつなぐことです。具体的には医療と別のジャンルをどう有機的につなぐかを試行錯誤しています。例えば僕にとっては医療と芸術は同じ根っこから生まれた別の果実だという実感があります。医と芸の共通の根っこへ立ち戻り、医療と芸術を含んだ全体を取り戻す活動を展開していました。そうしたときに、東北芸術工科大学の学長でアーティストでもある中山ダイスケさんから山形ビエンナーレの芸術監督の仕事を拝命しました。コロナ禍でもあり、2020年はすべての企画をオンラインで実施しました。当時、すべての芸術祭は中止か延期されていましたので、文化や芸術の活動が不要不急とされた渦中に、山形ビエンナーレを実現できた価値は大きかったと自負しています。実は櫛野さんの活動には、非常に共感するところが多いのです。独学で表現活動を行う人びとを紹介した『アウトサイドで生きている』はいろんな観点から歴史に残る名著だと思っています。
 『アウトサイドで生きている』(タバブックス/2017)
『アウトサイドで生きている』(タバブックス/2017)
櫛野 うれしいです。
稲葉 櫛野さんの立ち位置、相手との距離、観察者としての視点の距離感が素晴らしいです。あと、どの相手にインタビューするときにも、何年に生まれ、長男か次男かとか、そういう個人の歴史や来歴から話を始められている。僕はそうした本人の歴史を尊重する立ち位置がとても好きです。
櫛野 お医者さんのカルテに似ているかもしれませんね。僕が取材を続ける動機は、なぜそうした表現活動に行き着いたのかを知りたいからです。美術批評家の椹木野衣(さわらぎ・のい)さんが『アウトサイダー・アート入門』でも書かれていますが、ものすごい表現をされる方の中には、家族との離別や自然災害、戦争経験など、何かしらの逃れられない宿命のようなものに遭遇していて、そうした苦難を乗り越えるために、言い換えれば「生きる術」として表現しているのではないかと思っているんです。つまり社会的処方じゃないですが、何かを自分で生み出すことでセルフケアをしているんだと思うんですよ。そのために細かくお話を聞いています。
稲葉 櫛野さんはそれを「欠損」と表現されています。「不幸」とは少し違っていて、この「欠損」という表現が村上春樹のようなニュートラルな表現ですごくいいなと思ったんです。「欠損」を災難と取るか、人生の流れと取るか次第で、「不幸」という言葉をあてはめていいのかどうか、という櫛野さんのためらいや礼節が感じられるんです。
櫛野 おっしゃる通りです。たとえば、僕は「アール・ブリュット」という言葉は意図的に使わないようにしています。かつて日本では、「アール・ブリュット」という言葉が「障害のある人の芸術表現」と誤認されることで、純粋無垢な人たちが描いた芸術を連想させるという懸念がありました。障害のある人の表現だけではなく、死刑囚やヤンキーなど、いわゆるアウトローとされる方々の表現も本来の意味の中には含まれているので、「アウトサイダー・アート」という言葉を意図的に使用しています。ただ、取材をしていくにつれ、自分の顔にガムテープを貼って変装するサラリーマンなど、身近な人たちからも表現が生まれていることがわかりました。そうなるともはや「アウトサイダー・アート」ですらありません。だからこそ「アーツカウンシルしずおか」ではすべての県民が表現者になることを目指しています。アートというと高尚なもの、自分とは縁がないと思っている人が多い。でもそんなことはなくて、誰もが何かしらの表現をしています。人は誰でも表現者になり得るという思想は、僕のこれまでの仕事の延長線上にあるんです。その中でも特に高齢者の表現へ興味を抱いているというわけです。
 スギノイチヲさんが扮装した「パブロ・ピカソ」
スギノイチヲさんが扮装した「パブロ・ピカソ」
稲葉 僕も高齢者施設を回っていますが、施設によっては暗いトーン、なんだか希望がないみたいなトーンが醸し出されている施設がありませんか。職員は何とかしようと最初はもがいていても、その巨大な闇のような空気に飲み込まれて、もうあきらめてしまって、ただただ日々の業務をこなすだけになっている。もちろんすべての施設がそうではありませんが、重い空気に包まれた施設もありますよね。
櫛野 それ、わかります。プライベートな話ですが、義母が病気になり、最重度の介護が必要となりました。ずっと妻と一緒に看ていましたが、静岡へ移住するにあたって今は老人ホームで生活しています。義母はもうほとんどしゃべれないし、自分でご飯も食べられなくなっているけれど、僕らにとっては非常に尊い存在です。そのときに僕は人と人をつなぐのがアートの役割だと思っていて、もし義母が筆を持って絵の具の一滴でも垂らしたら、僕らはそれを素晴らしい表現として受け止めるでしょう。身近な人がそれで笑顔になったり、幸せになったりする力がある。だから高齢者の方々の表現に希望を見出して、追いかけているんです。
稲葉 現状の施設では「お絵描きしましょう」、「『おててつないで』を歌いましょう」と言った、決められたフレームワークの中での活動になりがちですね。決められたカリキュラムをこなしているような感じで。場の環境をどう整えるかで高齢者もまったく違う様子を見せるはずですし、それは医療や介護従事者にとっても同じだと思います。無意識の背後から場を規定するものに対して、どう挑めばいいのか、場そのものの空気をよくするには何が大事なのだろうかと、いつも考えています。
櫛野 老人施設で高齢者の方々に提供される表現活動は、高齢者の幼稚園みたいだと揶揄されることもあると聞きました。人生120年時代と言われ、ひょっとすると定年退職後の人生の方が長い場合だってあり得るでしょう。これでは超高齢化社会において、明るい未来が見えません。義母を救うと言ったら大げさかもしれないけれど、彼女自身が「生きていていいんだ」と言えるものを何か見つけたいと思っているんです。
稲葉 施設には職員と高齢者との関係に無意識の上下構造みたいなものが隠れています。当事者は気づいてないのですが、実はすごく影響を受けています。病院含めた医療の場自体がそうです。場の裏側に潜む構造そのものをひっくり返さない限り、対等でフェアな関係はなかなか生まれません。そうした無意識に許容して同意してしまっている見えざる前提に対して、櫛野さんは果敢に挑戦しているなと思うんです。
 巨大生物が都市を破壊する危機を描く稲田泰樹さん
巨大生物が都市を破壊する危機を描く稲田泰樹さん
櫛野 例えば、「音楽のまち」として知られる静岡県浜松市では、アマチュア音楽家がたくさんいらっしゃるので、そういう方々が老人施設の高齢者にマンツーマンで演奏をするアイデアを検討しています。しかし「聞かせてあげる」だと演奏家が上位になってしまうので、高齢者が指揮棒を振って、そのリズムに合わせて演奏してもらうとか、そういう新たな関係性がつくれないかと考えているんです。見方を変える、立場を逆転させるのは、それこそアートの力ですから。
稲葉 まだ詳しくは言えませんが、僕も、高齢者をテーマにした企画を考えているところです。この高齢化社会において、高齢者を尊敬できる社会にならないと希望が持てません。高齢者の方にはむしろ僕らを引っ張っていってくれる輝ける存在であってほしいんです。
櫛野 老化は誰もが確実に通る道なので、何かそこに活路を見出しておかないと、人生をよりよく生きる希望が持てないですよね。ですから取材する方には常に敬意を払っているし、僕自身、教えられることはすごくありますね。でも今までたくさんインタビューしましたが、多くの方々が「いい人生だった」と話してくださいます。
 「不動明王」の磨崖仏を掘り続ける田中唯支さん
「不動明王」の磨崖仏を掘り続ける田中唯支さん
「人生をかけている」その裏に流れる情熱に惹かれる
 「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展」より
「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展」より
稲葉 櫛野さんが『アウトサイドで生きている』で取り上げている方々の記事を読むと、こんなふうに表現をしてもいいんだ、自由に生きていいんだ、と、思わず笑ってしまうような勇気をもらう人が多いと思うんです。取材されている一人ひとりのことを読むと、僕らの周りに普通にいる人じゃないか、と感じる身近さがありますよね。
櫛野 そうなんです。本当は僕がわざわざ足を運んで取材する必要はなくて、各地でそういう人が称賛されたり、主役になってくれればいいんですけどね。
稲葉 櫛野さんはいろんな猛者たちと出会っています。実際に連絡を取られて、お宅に行ったりされていますけど、恐怖心とか、まったくないんですか。
櫛野 めちゃくちゃありますよ。でももう慣れちゃっていると言いますか。僕は連絡先も公開しているので、いろいろな方から連絡が来ますし、ギャラリーにいきなり作品が届いたりもする。そういう因果も含めて全部背負っていかなければと思っているんです。
稲葉 飛び込むことで見えることはありますよね。病院にやってくる患者さんも、よそ行きの顔しか見せません。これで果たして患者さんのことを本当に理解できるのかと思い、在宅医をやり始めて15年ぐらいになります。お宅に伺うと、その人の表現がすべて見えます。どういう毛布を使い、家具をどう配置しているのか、部屋に何が置いてあるのか、台所回り含めて、自宅の表現、空間のつくり方を見ていると、生きる部分に近いコアな表現がぐっと伝わってきますね。
櫛野 それだけ芸術と生活は地続きなものなんですよね。だから表現者として特定の人だけが称賛されることにすごく違和感を覚えるんです。
 創作仮面館
創作仮面館
 創作仮面館
創作仮面館
稲葉 廃材でつくった仮面が山のように置かれている創作仮面館の館主さんが衝撃でした。ずっと一人で生きてきたと語っているのに、実は奥さんもお子さんもいたことがわかったというオチも驚きました。ただ、医療現場でもそういうことがよくあるんです。情熱いっぱいに話してくれるから、リアリティや説得力があって引き込まれるじゃないですか。でも家族に聞くと、それは違いますよ、嘘ですよ、本人の妄想ですよと言われて、何が真実なのかわからなくなるんです。
櫛野 取材しているとは言え、話が本当かどうかはわからないし、僕も追求するつもりはないんです。創作仮面館の館主は2018年に亡くなりましたが、ご家族とは今も話しますけど、お線香も上げに行っていません。館主の素顔を見たくないし、知らないままでいたい。そう思わせることも含めてアーティストかなとも思うし、もしかしたら館主は、天国で「あっかんべー」をしているのかもしれません。
稲葉 ドキュメンタリー畑の人だと真偽をとことん追求してしまうかもしれませんね。ただ、謎は謎のまま終わらせることも大事です。そうした曖昧さを大切にする距離感が、いいバランスだと思いながら本を読みました。どんな人にも曖昧さを保ったほうがいい場合がありますからね。
櫛野 不思議なことに僕はそういう方々と気軽に仲良くなれるんです。でも僕はコミュニケーションは、むしろ苦手なほうです。じゃあなぜ仲良くなれるのかと言えば、かつて働いていた障害者福祉施設では、コミュニケーションに障害のある人が多くて、視線の動きや雰囲気、手をつないだときの感覚など、ある種のノンバーバルな会話を養ってきたんです。だから距離感がすぐに近くなるんだと思います。
稲葉 そう言えば僕もすっかり忘れていたことを思い出しました。実家に帰ったときに巨大な缶が10個ぐらいあって、その中に僕が描いたビックリマンチョコを模した絵が何万枚もあったんです。当時、ビックリマンチョコはすごい人気で、熊本の田舎では全然買えませんでした。それでしょうがなく自分で描いていたんでしょう。それぞれのキャラクターの名前には「鬼」「魔」「天使」「助」がついていて、子どもの自分なりに制限やルールを決めて創作しているんだと驚きました。ここまでやれたモチベーションはやっぱりビックリマンチョコが買えない、でも欲しい、じゃあどうやってその矛盾を解決するのか、という切実な思いから出てきているのかな、と、当時の自分を思いましたね。
櫛野 ないからこそ想像し、創造する、それは人間だけができることですから、面白いですよね。
稲葉 僕も今はなんとか社会に適応して生きていますけど、『アウトサイドで生きている』に登場する方の生き方には憧れます。社会が何かおかしいと1日に3回くらい思うんですけど、そんなおかしい社会に適応するのではなくて、自分で世界をつくり、その中で孤高に生きている人たちは気高くてかっこいいなあ、と。
櫛野 そうなんです。だから「作品を見てください」という依頼はめちゃくちゃありますが、年齢の若い方の表現だと心に響くものがない場合が多いんです。人生をかけているという裏に流れる情熱にドキッとしてしまう。彼らは自分だけの独自の評価軸を持っている。僕らはどうしても誰かに相談したり、誰かに頼ったりして生きていますが、彼らはそうじゃない。そこに絶対的な自信と覚悟があるから、ついつい惹かれてしまうんです。彼らのお話は「常識やルールとは何か」を考えるきっかけにもなっています。そこまでの破天荒な生き方はできないけれど、生き様の指針にしたいなとは思いますね。
稲葉 病気も芸術もそうですが、社会的に与えられた「概念」や「固定観念」を超えた場所で生きている人たちの中から生まれてきた表現に、底知れない純粋さや強さを感じます。芸術の表現自体が、アート業界の流れや流行に乗っかる必要はないのではと思うんですよね。最大公約数になりえない、人類の中でも極めて個別で、決して一般化できない究極の個の世界。そうした個の世界で生きる人たちに光が当たることで、社会の枠組も真の意味で多様な社会になるのではと思います。
櫛野 そういう意味で、最初にお話しした「すべての県民が表現者」ではないですが、一般の人たちにも、実はそういう表現の種はたくさんあるんですよということを、今この仕事で訴えているところです。
障害者のアートはすべてを背負う覚悟が重要
さっき、アウトサイドな方々と出会ったらそのすべてを背負う覚悟とお話しされましたが、櫛野さんは障害ある人のアートについても同じ思いでいらっしゃるんですよね。
櫛野 そのへんが今の、障害のある人のアート活動の問題点だと思っていて。この表現が面白いから世の中に出そうと、職員や周りの支援者が動いたりしますが、その人の人生が大きく変わってしまう恐れがある。障害のある人がアート活動をするというのはいいことでもあるのですが、一方でアート業界に投入してしまうことにもつながるんです。「その後のことは知りません」みたいな雰囲気になってはいないか。僕も施設を辞めてずいぶん経ちますが、僕が発見してしまった人たちは未だに絵を描いていらっしゃる。描かされていると言ってもいいかもしれません。そこはすごく責任を感じています。だからこそ関わった人のすべてを背負っていかなければと思うんです。
 櫛野展正さん
櫛野展正さん
稲葉 今の言葉は本当に重いなと思います。
櫛野 お医者さんもそうじゃないですか?
稲葉 その通りです。医療者の些細な言葉一つも人生を変えてしまうくらいの重みがありますよね。でもそうした言葉や場の力を医学教育では学びません。プロの医療者になってからもフィードバックがかかりません。だからこそ、自分の言葉や行動に責任をもち、結果も含めてまるごと全部引き受ける覚悟がないと、いい仕事にはつながらないと思います。
櫛野 もしほかのキュレーターさんたちと違うところがあるとすれば、僕は現場ありきなんですよ。常に側に寄り添いたい。もともと僕は障害者施設で生活支援もしてきましたし、自閉症スペクトラムの方に対応する専門的な資格も取っています。そしてアートは、その人がよりよく生きるための、支援の引き出しの中の道具の一つとして考えています。もしも健常者と障害者の世界があるとしたら、今のアートの支援って、いわば障害のある人を健常者のフィールドに引き込んでしまっている気がします。そうじゃなくて、まずは僕らの方から障害のある人たちの世界へお邪魔すべきだという姿勢が重要だと思っています。
多くの人たちは「福祉」と聞くと、「介護を受ける」というイメージが一般的かと思います。福祉とは英語で「Welfare」「Well-being」と言って日本語では「よりよく生きる」という意味の言葉に解釈できます。「福祉」とは本来は、生き方を探求する学問だと思っていて、実はすごくクリエイティブなものなんですよ。
 稲葉俊郎さん
稲葉俊郎さん
稲葉 アートという通路があれば、ある人はすーっと思いがけないものを引き出せるかもしれません。もちろん、またある人はアート以外の別の通路が必要なのかもしれません。そうした個々人での表現の通路を考えると、医療現場で何か出口がなく閉塞した状況の中でも、芸術という引き出しがうまく使えるのではないかと、自分なりに工夫しながらもがいています。やはり、謎を含んだ芸術の中には、医療や福祉を別次元で突破する鍵があるのではないかと思うことが多いんですよね。櫛野さんの取り組みには、どんな人にも開かれた大きな希望や可能性を感じます。
文化芸術の秘めている「力」について紹介したい。これも、このサイトで追いかけていきたいことの一つです。生きることにつながる文化芸術の可能性について、また決して限られた人のためのものではないというお二人の話はとても興味深いものでした。高齢者の、アウトサイダーの、障害のある人の、という3つの切り口で語っていただきましたが、通底する、「誰もが表現の種を持っている」という言葉が心の中に響いています。