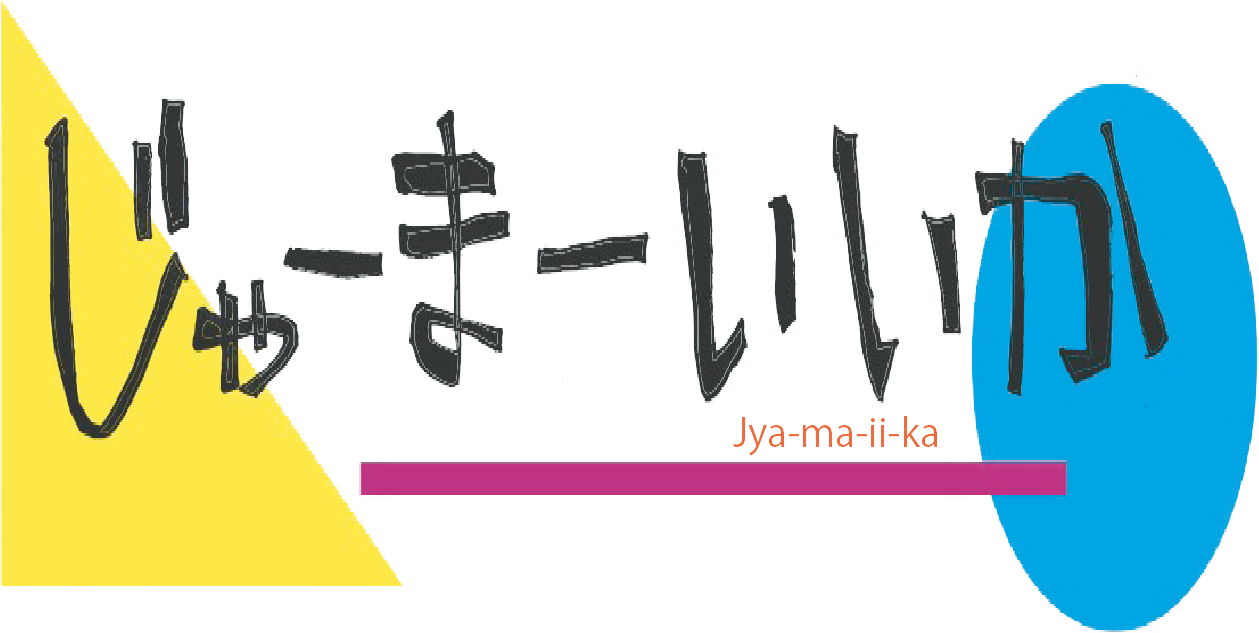第6回 いろんな表現がにょろにょろ
【刺繍】
HIROMIさんは風の工房に通い始めた当初、とても怒りっぽくて、急に大声を出していた。どうやら幻聴に振り回されていたらしい。仲間たちも何だか近寄りがたい感じだったので、彼らとも少し距離を取りつつ、何かHIROMIさんが夢中になって取り組めるアートな活動はないものかとあれこれ考えていたとき、そうだチクチクと刺繍はどうか、それも細かい作業ではなく、わかりやすくてざっくりしたものがいいと、さっそくコーヒー豆を販売している知り合いから、コーヒー豆を入れる麻袋をいただいてきた。

そして太い針と毛糸を使って刺して返すという、いたって単純な刺繍を提案してみた。絵柄は関がざっくりと描くのだが、罫線のように油性ペンで線を入れておくと、彼女は自分の考えた色の毛糸で刺して返すを繰り返した。作業台も彼女のやりやすいように手づくりした。HIROMIさんはもともと丁寧に作業をする人なのだが、「これ、面白い」と言って夢中になってくれた。するとどうだろう、いつの間にか大声を出したり、怒り出したりすることが減っていった。

この刺繡にはほかの仲間も興味を覚え、MIYA君、SAYAKAさんもいい感じでハマった。毛糸を確保し、針に糸を通して渡すというサポートをしながら、日がな一日のんびりと仲間が音楽を聴きながら刺繍をしている風景は良いものだと、しみじみ。とはいえ毛糸が足りない、ビンボーな風の工房にお金の余裕はない。そこで、かりがね福祉会が真田町内全戸に配布していた機関誌と町の社会福祉協議会の広報誌に「お宅で眠っている毛糸を譲ってください」と掲載してもらったところ、びっくりするほどの毛糸が集まったのだ。感謝である。

【ボールペンアートのハジマリ】

当初こちらで用意した画材はクレヨン、絵の具、色鉛筆だった。仲間たちの多くは殴り描き、色もガシャガシャとした塗り方で「ほい、できたよー」とばかりに次々と紙を使いまくるため大量の作品(?)がたまっていった。今の僕ならばそれもいいのではないか、と思えるのだが、当時は「できればきちんと、集中して、時間をかけて丁寧な塗り方をしてほしいなあ」というのが正直な気持ちだった。また仲間も増え、次々と作品が生まれても、僕や数少ないスタッフでは対応できない。そこでハタと考えた。時間をかけてゆっくり絵を描いてくれる方法はないものか、と。なぜなら絵を描くことに集中してくれている間に、わりと障害の重い人へのアプローチに時間を使えるからだ。

僕は「そうだボールペンはどうだろう!」と思いつき、ホームセンターに出かけ、さまざまな色のボールペンを大量に買い込んできた。そのカラフルなボールペンを見て最初に目を輝かせたのは、刺繍にハマっていたHIROMIさんで、次々とユニークな作品を生み出し始めた。それを見ていた仲間からもボールペンを手にして描き出す人たちが出てきて、一時期は“ボールペンアート”ブームになった。なにせ1枚の絵を仕上げるのに何日もかけてくれるのだから、「こりゃあいい」と僕はニンマリした。
まぁこんな僕の姑息な思いつきで、風の工房でのボールパンアートは始まった。

HIROMIさんは頭の中に浮かぶさまざまなイメージを次々に表現していく。ボールペンで空白を埋めていく時に紙の位置を変えるのため、線の向きが変わり、同じ色でもそこに独特の模様が生まれる。豊富なイメージが泉のごとく湧き出る彼女を見ていて、僕はいつか枯渇してしまわないかといらぬ心配をしたほど。しかし、僕がかりがね福祉会を離れてからではあるが、HIROMIさんはある日突然逝ってしまった。今は残された作品は自宅に飾られ、お母さんが管理されていると聞く。
【ならべアート】
重い自閉症という障害があるUTTIが、ある日OIDEYOハウスから姿が見えなくなった! と思ったら、裏庭で石をほじくり出してそれを並べていた。そんな行為がよく見られるようになって、スタッフがそれを面白がるようになった。スタッフが川から適当な小石を拾ってきて、ほかの仲間たちが絵の具で色をつけてバケツに入れておくと、UTTIはそれを持ち出して裏庭で並べ終えると、スタッフが毎日写真に撮った。
お母さんに聞くと、並べるという行為は小さいころから家の中でも毎日のようにやっていて、引っ張り出したティッシュで廊下にまるで雪が積もったかのように並べられていたそう。また別の日には、こたつの上に洗濯ばさみ、ブロック、お菓子の包装紙、果ては食べた後のぶどうの種まで並べた。それを世間では『自閉症の人のこだわり』という言葉でくくってしまうが、僕らはそれを理解はできないもののUTTIなりの法則で並べているのだろうと考え、『UTTIのならべアート』と呼び、面白がった。

作品展でも会場の床の上に本人に石を並べてもらって、ほかの仲間たちの作品と共にインスタレーションとして展示した。ある美術館のフロアでUTTIが石を並べるように段取りしたはいいが、UTTIの『ならべアート』を始めるスイッチが入るまでに1時間以上もかかり、付き添ったスタッフがひたすら待っていたことを思い出す。
お母さんは「家で余計なことして困るんです、ティッシュがいくらあっても足りない」と当初はおっしゃっていたが、「これはカッコいい現代アートですよ」と伝えると、「そうなんですかあ? 無理やり止めさせればパニック起こしますしね、安いもんだと思えば、ま、いっかあ」と言い、数日後にUTTIを床屋さんへ連れていき、モヒカン刈りにして「うちの子は現代アーティストなんですねえ。あはは」とうれしそうにしていた。
なんて素敵なお母さんだろうか。本当はそれまで重い障害のわが子を育てるのに並々ならぬ苦労を重ねていて、僕らもその苦労話をたくさん聞いていたのだが。
〈つづく〉
著者プロフィール

- 関孝之
- 1954年生まれ。社会福祉法人かりがね福祉会で勤務しているときに「風の工房」を開設して障害者の表現活動支援を始める。アートパラリンピック長野の実行委員、スペシャルオリンピックス長野県大会のアートディレクターを務め、2014年からは、NPO法人ながのアートミーティング代表として障害者のアート活動を応援する活動に専念し、出前アートワークショップやアートサポーター養成講座などを行っている。信州ザワメキアート展実行委員長。