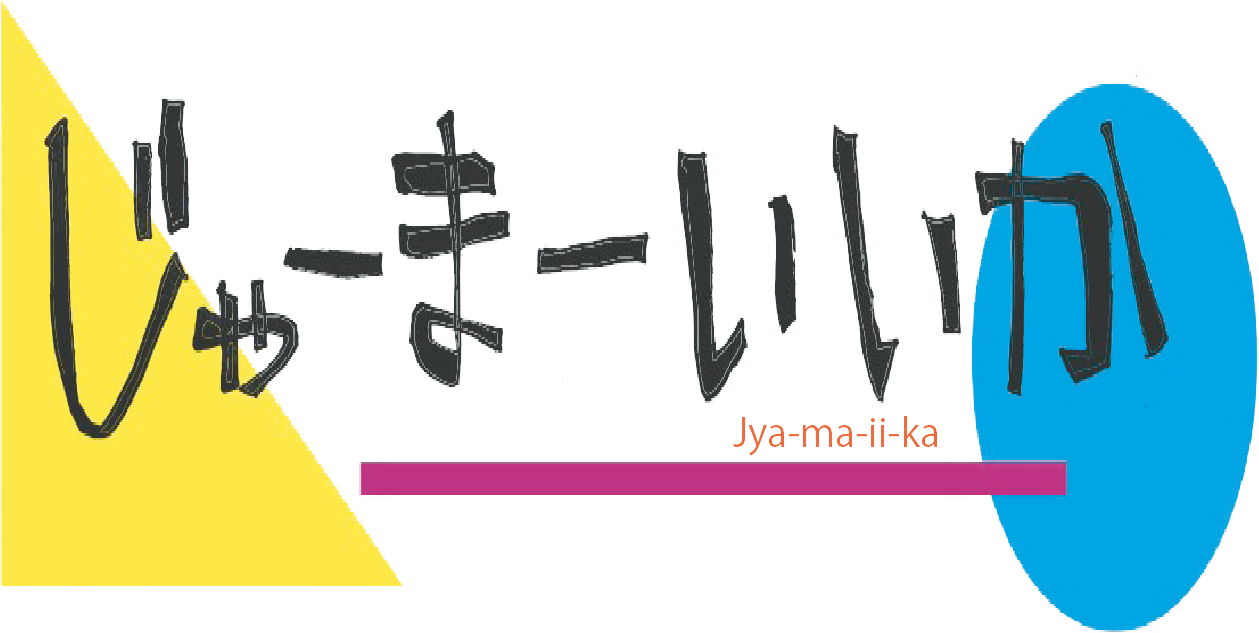第1回 つらつら振り返って
『なんで、あなたは障害のある人のアート活動を始めたの?』という質問をよく受ける。しかし、だんだんと記憶が薄くなって、『さていつから?』『どうしてだっけ?』が曖昧になっている。まあ、その前に、なんで僕は障がい者福祉の仕事に足を踏み入れたのかから始めなければならないかもしれないが、そのことはいずれ触れることにする。
今から30年ほど前、僕は職員として所属していた社会福祉法人かりがね福祉会のバックアップのもと、障がいのある人5名と自分の家族とが実験的に小規模で共同生活をする『風の工房』を開設し、活動をはじめた。当初はパンの製造販売、農作業、陶器の製作などを通じ、それぞれの活動において、障がいのある仲間とそれぞれにできることを協力しあっていくことで、いずれはその集団として自立した生活を実現しようと夢見ていた。しかしそんなに甘くはない。収益はさほど上げられるわけもなく、次第に僕は仲間たちに『きちんとやって!がんばって!これじゃあ売れない!』といった言葉を投げかけるようになり、対等な関係、と言いつつ現実はひどい上から目線で仲間を見ている自分になっていった。日中だけ『風の工房』に通ってくる仲間も増えていたこともあるのだが、『こういう状態って自分が望んだことなの?』と自問自答する日々が続いた。何より仲間たちが僕の顔色をうかがうようにもなり、これじゃあ僕は独裁者じゃん。この小さい集団として自立することばかり求めていて気が付いたら間違った方向に走っていたのだ。
ある日のこと、粘土の作業場でお皿や小鉢とかの器を作っていたのだが、それはどう考えても売れるシロモノじゃあないと、ぶつぶつと文句を言って、仲間が作っていた器をつぶしていた。仲間たちはそんな僕の顔色を窺っている。その時の彼らが作るそのいびつな形は本当にいけないのか? それは僕自身が売れるものとはこんなもの、という勝手なイメージを持っていたからであり、なんと狭量な考えだろうかとふと考えた。ちょうどその時、僕は画家の田島征三さんが滋賀県の信楽青年寮に入り込んで、そこで生まれる粘土の造形を高く評価して本にした、『ふしぎのアーティスト』という本を読み始めたときだったのだ。田島さんは青年寮でそこの寮生さんが作り出したものを、職員がいびつだとか売れそうもないからと評価していなかった現場を見て、これこそがおもしろいカタチだし、アートとして素晴らしいと職員さんたちに伝えて以来、素晴らしい造形作品が生まれ始めたことを書いている。全く僕がやっていたことを指摘されたように思い、鈍い自分の頭を殴られたようだった。
『こんなつまらない粘土はやめようか。』と何気なく仲間に伝えたところ、彼はうんうんと頷いて、その作業場を出ていってしまった。僕の勝手な価値基準を彼らに押し付けていたことを痛烈に問われた瞬間である。その場に残された僕はしばらく呆然としていた。このジケンは今でも鮮明に思い出される風景なのである。第2回目につづく
※『風の工房』では障がいのある人を仲間と呼んでいたが、今の時代なら利用者と言われ、職員は支援者と言われる。支援者と利用者の関係……どこか違和感を持つ僕である。
著者プロフィール

- 関孝之
- 1954年生まれ。社会福祉法人かりがね福祉会で勤務しているときに「風の工房」を開設して障害者の表現活動支援を始める。アートパラリンピック長野の実行委員、スペシャルオリンピックス長野県大会のアートディレクターを務め、2014年からは、NPO法人ながのアートミーティング代表として障害者のアート活動を応援する活動に専念し、出前アートワークショップやアートサポーター養成講座などを行っている。信州ザワメキアート展実行委員長。