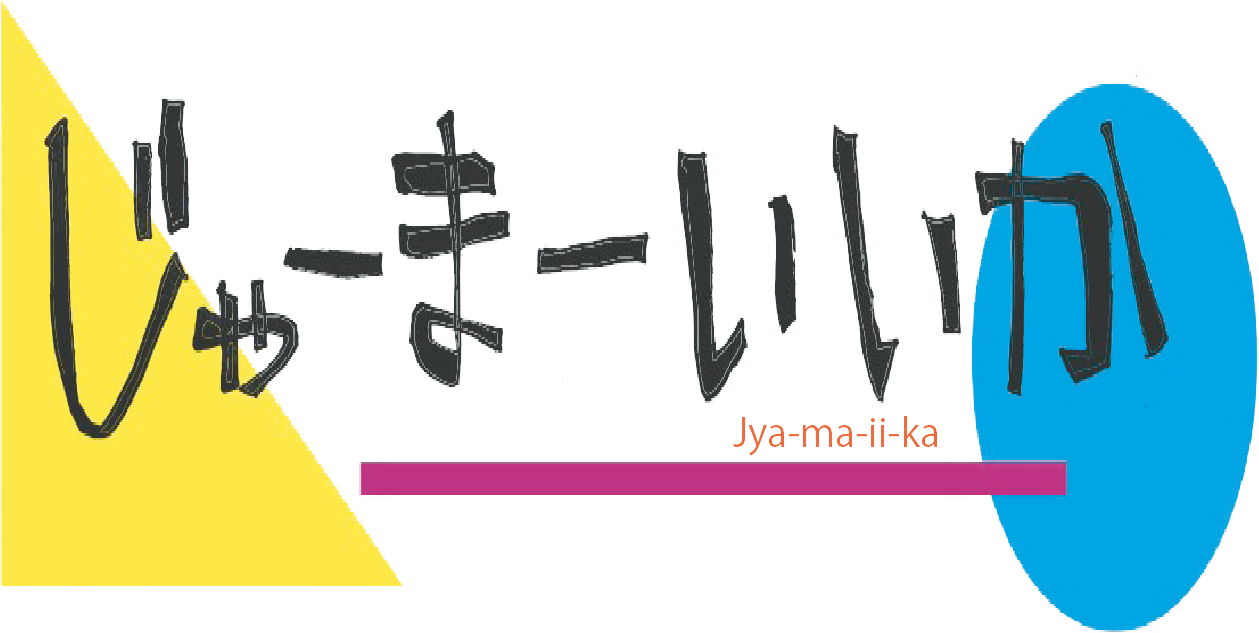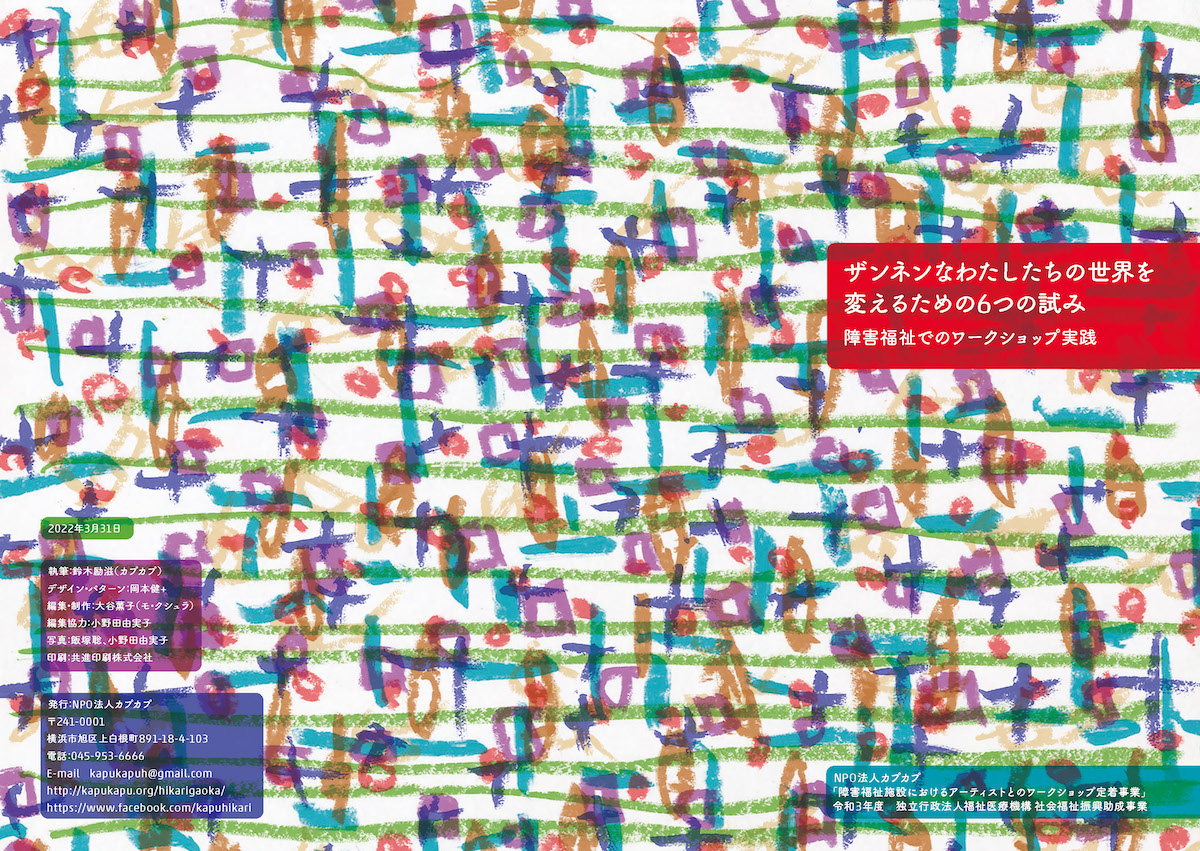[対談]鈴木励滋さん(生活介護事業所カプカプ)×唐川恵美子さん(ほっちのロッヂ)
横浜市旭区にある生活介護事業所カプカプの所長である鈴木励滋さんは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の助成を受けて2021年に「障害福祉施設におけるアーティストとのワークショップ定着事業」を実施した。手応えを得て、この活動を全国に広めたいと考えている。軽井沢町にあるケアの文化拠点を謳う「診療所と大きな台所のあるところ ほっちのロッヂ」でアートコーディネータを務める唐川恵美子さんは医療福祉の現場にアーティストが入り込む滞在制作を展開している。日常風景の中にアーティストという存在を迎え入れることで生まれる気づき、新たな価値観の醸成によって、鈴木さんは障害のある人のための施設、唐川さんはケアの現場と社会との関係の結び直しをしているという点で共通するような気がした。新たな未来に向けた可能性のようなものを伺いたくて、対談をしていただいた。
 鈴木励滋さん(撮影:日夏ユタカ)
鈴木励滋さん(撮影:日夏ユタカ) 鈴木励滋(すずきれいじ)
生活介護事業所カプカプ所長、演劇ライター。群馬県高崎市生まれ。1998 年には横浜市旭区のひかりが丘団地商店街で「喫茶カプカプ」を、2009 年には斜向かいに「工房カプカプ」を開店。同年にNPO法人化し、2017年からは生活介護事業所として運営。現在は、横浜市内にある〈カプカプ竹山〉と〈カプカプ川和〉を含んだ3事業所合わせて総勢60名近いメンバーさんが通い、喫茶店の運営、お菓子づくり、リサイクル品の販売などを行なっている。演劇については「埼玉アーツシアター通信」、「げきぴあ」、劇団ハイバイのツアーパンフレットなどに執筆。『生きるための試行 エイブル ・アートの実験』(フィルムアート社、2010年)にも寄稿。師匠の栗原彬さん(政治社会学)との対談が『ソーシャルアート 障害のある人とアートで社会を変える』(学芸出版社、2016年)に掲載された。
 唐川恵美子さん(©️清水朝子)
唐川恵美子さん(©️清水朝子) 唐川恵美子(からかわえみこ)
「ほっちのロッヂ」アートコーディネータ。旅するポテサラ屋店主。福井県三国町出身。じゃがいもが好きという理由でドイツ語を専攻し、学生時代はウィーンに留学。大学卒業後、東京のコンサートホールに勤め、年間120本以上の企画運営を担う。その後、2016年に地域おこし協力隊として福井へUターンし、坂井市竹田地区へ。音楽家が老々介護世帯を見守る「アーティスト・イン・ばあちゃんち」を主宰。2018年より(公財)坂井市文化振興事業団に職員として勤務。現在は軽井沢町にある「診療所と台所のあるところ ほっちのロッヂ」にてアートコーディネータを務める。ピアノ弾きでもある。
まずはお二人の自己紹介からお願いできますでしょうか。
鈴木 私は実は物書きになりたかったんですが、文学部には入れてもらえなくて、浪人を経て拾ってもらえたのが法学部。単位とか関係なく他学部でも興味ある講義にはもぐってました。「日朝関係史」とか「比較文化論」とか。「政治社会学」のゼミで「差別」とか「共生」というテーマを理屈で学んでいました。私の恩師の担当編集者が変わった人で、横浜で出版社と自然食のお店をやってたんです。お店で精神障害のある人を雇ううちに自分たちでもそうした場をつくろうと動かれていました。そのころ私がブラブラしていたので、「見学だけでも来ないか?」と誘われて、顔を出したら「職員の鈴木君です」と紹介されて(苦笑)。仕方ないから立ち上げだけでも手伝うかと思っていたら、いつの間にか25年ほどが経ち、今は生活介護事業を行う事業所3カ所を運営し、54、5名のメンバーさんが通っています。
 カプカプ(撮影:阿部太一)
カプカプ(撮影:阿部太一)
 カプカプのメンバーさんとともに
カプカプのメンバーさんとともに
カプカプさんは喫茶店として、個性あふれるメンバーさんがお客さんをお迎えしているんですよね。
鈴木 なんでも山盛りが大好きで、洗いカゴのコップや店のミルクをいつも山盛りにしている沼舘さん。向かいの整骨院に常連のウエハラさんがいると杖を奪っ……いや、手を引いて連れてくる中原さん。「最重度」と言われる星子さんは喫茶の奥でよく横になっていますが、私たちは星子さんに会いに来るのもお客さんのモチベーションの一つになるので、そこにいてくれることが接客だという考えです。中原さんはダンディな常連タカギさんの姿が見えるとくねくねと不思議なダンスを踊るんです。最初はタカギさんも戸惑っていましたが、「これは歓迎しているんです」と伝えると喜んでくださって、今は向かいの八百屋で買った果物を差し入れで持ってきてくれるようになりました。ほかに楽器を鳴らしたり、それを自作したシルクハットと燕尾服を着て指揮をしたり、販売してる古着でコスプレしてみたり、なぜか道を行き交う人を応援するとか、盛り立ててくれるメンバーさんがたくさんいます。そんなにぎやかなことを商店街の真ん中でやっていても許されるくらい、25年近くご近所づきあいをせっせとやってきました。メンバーさんにはカプカプの目指すザツゼンさそのまま、一人ひとりが思い思いに表現してもらって、それを地域の皆さんとつないでいくことが私たちの仕事だと思っています。そのぶん周りのお店の雑務を一手に引き受けています。
 沼舘さんが山盛りにしたミルク
沼舘さんが山盛りにしたミルク
 カプカプ祭り
カプカプ祭り
唐川さんが所属する「診療所と台所のあるところ ほっちのロッヂ」もユニークな活動をされていますよね。
唐川 ほっちのロッヂは2019年9月から訪問看護ステーションとして事業をスタートして、2020年4月から在宅医療を担う診療所と病児保育、医療的ケア児の居場所である児童発達支援・放課後等デイサービス、高齢者の方も介護を受けながら過ごすことのできる通所介護などのケア事業を展開してきました。そんな中、私は2020年4月から文化企画担当として、医療も福祉もごちゃ混ぜになっている空間の中で文化芸術活動を実施していくことをミッションとしています。実際には、1年目は新型コロナウィルスの感染拡大や立ち上げ期の整えのためほとんど動けず、2021年から実質的に文化事業のスタートを切りました。メインの事業は、アーティストの滞在制作と地域の文化活動支援の二軸です。滞在制作は、ほっちのロッヂにアーティストをお迎えし、主にケアスタッフの活動にスポットを当てる形で創作をしてもらっています。これまでに、ダンサー、写真家、サーカスアーティストなど、さまざまなジャンルから参加してもらい、この2022年度は作曲家、造形美術家、米国のビジュアルアーティストなどを迎えてきました。地域の文化活動支援は本当にいろいろな形があります。隣接する風越学園の学校医として連携している関係で、子どもたちのコンサートの音響を私が担当したり、企画制作の助言をしたり。また軽井沢には作家さんが多いので、そういった方を講師に迎えて子どもたちのアトリエ活動をしたり、まちに住む方の個展をお手伝いしたりと、いろいろなつながりから関係を結んでいます。
 ほっちのロッヂ
ほっちのロッヂ
 障害のある子もそうでない子もアトリエ活動に混ざる
障害のある子もそうでない子もアトリエ活動に混ざる
 台所にはいつも美味しい料理やお菓子が
台所にはいつも美味しい料理やお菓子が
アーティストを入れて場を開くことで価値観が変わっていく
カプカプさんではアーティストのワークショップはどんなふうにされているんですか?
鈴木 その前にお伝えしておきたいのは、うちは「アートが特別」みたいな感覚はなく、日々のすべてが表現だと考えています。だからこそ、メンバーの皆さんが存分に表現できるような環境づくりをいろいろと模索していて、その一環として絵本作家・画家のミロコマチコさん、文化活動家のアサダワタルさん、ダンサー・体奏家の新井英夫さんのワークショップをそれぞれ隔月でやっています。
ミロコさんは東日本大震災の前後だったと思いますが、うちのメンバーでエイブルアート・カンパニー(障害のある人のアートを、デザインを通して社会に発信する組織)の登録作家である渡邊鮎彦さんの絵をご覧になって、彼と合同で展示をしたいと声を掛けてくださったんです。そこで良い関係が生まれ、カプカプに来てもらうようになって10年を超えました。ミロコさんは絵を教えるというよりも、描く楽しさを伝えてくれるんです。またメンバーさんがどんなことをやっても面白がる彼女の姿勢から、スタッフも学ぶんですね。「なんでも面白がっていいんだ」という空気で満たされていくと、学校の美術教育なんかで嫌な思いをした人、萎縮していた人が数年がかりで回復して絵を楽しめるようになる。
アサダさんのワークショップでは「ラジオ」をやっています。といっても、配信などはほとんどせず、喫茶店内に流している程度ですが。うちではメンバー一人ひとりの好きなことややりたいことをなんとかその人の「はたらく」にしたいと思っているのですが、なかなかわかりやすい仕事にならないものも多くて。好きなアイドルやアニメの話をする人たちがいたり、その人の得意なことについてアサダさんが聞き出してくれたり。最近はよくファッションショーをやってますね、ラジオなのに。
体奏家の新井英夫さんは体を動かすワークのためにいろいろな小道具を持ってきてくれるんですが、新井さんが呼びかけたことをせずに、楽器をいじり始める人がいても、新井さんは流れを強引に引き戻すのではなく、そちらに乗っていくんです。とにかく引き出しが多いし、パートナーの板坂記代子さんや音楽家のササマユウコさんもいるので、収拾つかなくなっても大丈夫だって自信がきっとあるんですよね。
そのくらいの人たちじゃないと、お任せしたくない。私がすごいと感じるうちのメンバーさんたちに、渡り合える人じゃないと失礼だと思うんです。つまりワークショップはメンバーに何かを教えるのではなく、存分に表現してもらえる場。それによって一人ひとりを肯定できる場になっているんです。そして、ワークショップ以外の日、つまり日常でもそうあるために、そんなアーティストたちの感覚をスタッフに少しずつ体得してもらう機会でもあるんです。
 店の壁にも描く(立っているのがミロコさん)
店の壁にも描く(立っているのがミロコさん)
 喫茶店内でカプカプラジオ(右端がアサダワタルさん)
喫茶店内でカプカプラジオ(右端がアサダワタルさん)
 新井英夫さんのワークショップ
新井英夫さんのワークショップ
唐川 私もこの1年は、ケアに関わるスタッフにとって当たり前になっている感覚や表現をくみ取り、豊かにしたいという意図でやってきたので、お話を伺っていて共通したものを感じました。去年、身体表現者の小林三悠さんが滞在制作したときは、最初に過去の作品を再上演してもらい、それを見たスタッフが感想を伝える手段として、いつもの診療・看護スタイルで小林さんと話した記録をカルテに残してもらった んです。スタッフは舞台芸術に慣れていなかったり、参加型のワークショップも苦手な人が多いのですが、普段の自分たちの日常の営みが表現活動の一部になるとか、知らないうちに自分も表現していたとか、そういうことに気づけるといいなと思って行いました。
鈴木 そういう事業はスタート時から意図されていたんですか。
唐川 はい。私が軽井沢町に来る前に、滞在制作をやりたいということで事業提案していました。ただ、スタッフの価値観を題材にするという方針は、実際に現場が動き始めてから自然に生まれていきましたね。
鈴木 福祉よりも医療の方が地域に入り込みやすいかもしれないですね。わかりやすく誰にとっても必要があるという意味でも。
唐川 本当にそう思います。ほっちのロッヂでは外来もやっていて、乳児検診や予防接種で元気な子どもたちもやって来るし、いろいろな事情で学校に行けない子たちの相談も受けています。一方で、高齢で定期に処方されている方、だんだん状態が落ちてしまっている方、認知症の方、病院で手術を受けて家に帰ってくる方へのケア、お看取りまで、本当にいろいろな世代、状態の方と出会っています。
鈴木 いろいろ仕掛けされているのは面白いですね。障害福祉の事業所の多くは契約した10〜20名くらいのメンバーさんをケアすることだけが仕事だと捉える傾向にあります。実際に行政の実地指導や監査がそういう形態だからというのもあって。つまり地域活動などは行政にはほぼ評価されないんです。だから、やる気があるスタッフがいても次第にやる気が失せてしまう。医療も福祉も別に地域で面白いことを仕掛ける必然性はないですもんね。
唐川 そうですよね。制度に乗っかってしまうと、「やりたいけど、やらなくていいこと」が増えてしまう。その結果、場所が閉じていってしまう。ほっちのロッヂでは、いったん制度を気にせず、実験的に動いてみる場面も多いです。SNSや企画を通した情報発信も、その一環ですね。写真家の清水朝子さんの写真展をやったとき、スタッフが撮影した日常のスナップも一緒に展示したんです。外来で来られた方がそれらを見ながら「障害のある子たちはかわいそうね」と言っている横で、当の本人たちがめちゃくちゃワイルドに遊んでいたりする。そういう様子を見ながら私たちは「あそこで元気に遊んでるので、大丈夫ですね」みたいなコミュニケーションを取ったりします。そうした環境があるから、あまり場所が閉じていかないんです。
 交換留藝(清水朝子さん)。スタッフ撮影によるスナップ写真の展示風景
交換留藝(清水朝子さん)。スタッフ撮影によるスナップ写真の展示風景
 交換留藝(清水朝子さん)。作品を見ながらスタッフ同士の会話やフィードバックがはずむ
交換留藝(清水朝子さん)。作品を見ながらスタッフ同士の会話やフィードバックがはずむ
鈴木 とにかく出会わせたい。そのために場を開く。共感します。「障害者」という一般名詞ではなく、一人ひとりが固有名詞を持っているということを当たり前に知らしめると同時に、その「かわいそうね」と言っているおばあちゃんも固有名詞を持った人たちで、固有名詞を持った者同士として出会う。そうするとお互いにかけがえのない人になるんです。中原さんがウエハラさんの杖を奪って連れてきちゃうみたいな状態は、側から見ているとえらいことに映るかもしれないけど、お互いの関係が成り立っていることで違う見え方がしてくる。そういうことを体験してもらうためにほっちのロッヂやカプカプのような場があると思うんです。唐川さんのところは、短い期間でそういう場として機能しているって本当に素晴らしいですね。
アーティストにも福祉と出会い、かかわってほしい
鈴木さん、「障害福祉施設におけるアーティストとのワークショップ定着事業」について伺います。
鈴木 うちで10年以上やってきたアーティストのワークショップを外に広げたいということは以前から考えていました。厚労省が障害のある人の芸術文化活動の支援を行うために、各県に支援センターの設置を進めています(障害者芸術文化活動普及支援事業)。全国のセンターが集まる連絡会があって、うちの取り組みを2020年に紹介したところ、すごく反響が良かったんです。ワークショップというやり方を具体的にご存じなかった方もあったようです。また全国の支援センターは福祉が母体の法人が多く、芸術文化とのつながりが薄い。だからかもしれませんが、皆さんがイメージしていたのは「アールブリュット」のようでした。そのインパクトと成功モデルがあるので、「障害×アート」となると、美術展の開催が多い。施設としても美術は取り組みやすいみたいですし。逆にワークショップとなると人手もいるし、手間もかかるんですよね。ダンスや演劇といった身体表現系は、全国のリサーチから見ても障害福祉施設でほとんど取り入れられていない。特に演劇はセリフや段取りを覚えてやらなきゃいけないものだという勘違いで敬遠されていて。そこを変えていきたくて、ワークショップという方法を提案したんです。反響があったのにそのあともなかなか広がっていく気配がしない。それだったら実際に動き出した方が早いだろうということで、WAM(独立行政法人福祉医療機構)の助成金をいただけたので取り組んだわけです。劇作・演出家の岩井秀人さん、山本卓卓さん、益山貴司さん、振付家・ダンサーの白神ももこさん、アサダワタルさん、新井英夫さんに6つの施設に継続的に通っていただきました。各事業所の要望を聞く、アーティストの思いを聞く、双方をつなげるという作業はカプカプでやるとき以上に慎重にやりました。でも「スタッフの価値観を変える」など狙いは同じです。それで旭区の自立支援協議会でネットワークを培い一緒にやってきた施設に声を掛けました。どこもほとんどアーティストとの付き合いはありませんでしたが、そこにうまくつながれば、全国2万カ所以上ある障害福祉施設に普及させる可能性が生まれると考えたんです。
ワークショップを実施した施設とは、それ以前から「D-1グランプリ」を催されていましたよね。
鈴木 横浜市の旭区にはカプカプと同規模の事業所が50カ所くらいあります。ここでネットワークをつくる中で舞台表現の「D-1グランプリ」をスタートしたんです。各事業所のメンバーさんが集って、旭区役所にある公会堂のホールで歌ったり踊ったり何でもいいからパフォーマンスを披露するイベントで、7、8年開催してきました。それがコロナで難しくなったために、映像化して、どんどんYouTubeに載せていくことにしたんです。今まで「D-1」に出ていた施設の中には、映像がつくれないと言ったところもありました。でも、スマホで撮ってもらって、それをこちらで編集してなんとか形にして、なんとか開催にこぎつけました。やってみると映像は施設にも家族にも影響があったみたいなんです。そこに見たことのないメンバーさんたちの楽しそうな表情があることで、本人もやりたくなるし、なぜうちの子は出ていないんだと言い出す家族もいて、参加事業所も増えていきました。この業界には名前出しも顔出しもNGの人は結構いるんです。でもそこを少しずつ崩していきたい。障害があることを恥ずかしいと思わなくてよいんだという当たり前のことをだれもが当たり前に思えるように。撲たちがなんとしてでも一人ひとりを肯定しつづけることで、社会の雰囲気が変わっていくように。僕らはそういう思いで仕掛けてきました。
 旭区の障害福祉のお祭り「あっぱれフェスタ」内で開催しているD-1グランプリ
旭区の障害福祉のお祭り「あっぱれフェスタ」内で開催しているD-1グランプリ
ワークショップの手応えはいかがでしたか? アーティストも演劇界でも注目のメンバーでしたね。
鈴木 僕が「社会の価値観を変え得る表現」をしてきたと信頼している人たちから、各所の要望に合う人を選びました。あと意識的に、今まであまり障害がある人たちとワークショップをやったことがない人にも依頼しました。「ほわほわ」に入ってもらった山本卓卓さんはワークショップ中に岸田戯曲賞の知らせがあって、お祝いに「ほわほわ」のメンバーさんが書いてくれた手紙を届けました。授賞式で報告書も配布させてもらいました。「むくどりの家」に入った岩井秀人さんのワークショップには共同通信やNHKが取材にきてくれました。
ワークショップについては私がレクチャーさせてもらったんですけど、「成果を出さなくていい」とか「ただ関係を結んでいくだけでいい」とか言ったら、最初は皆さん戸惑っていました。たとえば岩井さんは精神障害のある人たちの事業所で、毎回みんなの話を聴くんです。メンバーさんから出てきた「親と喧嘩した」とか「美容院でカットされてる間、なにをしゃべればいいかわからない」なんて話を「じゃあ、ちょっとやってみますか」なんて岩井さんが言って、スタッフも含めみなさんで再現してみるんですが、上演作品を目指すわけでもない。それでも、他者を演じてみることでやはり感覚が変わるんです。他者や世界の見え方が変わる。本当はカプカプでやりたいくらい面白かったですね。
一方で、私としてはアーティストにも障害福祉との関わり方があるんだということを知って欲しかったんです。そのことで新たな道が開ける。厚労省の事業に取り組んだり、舞台芸術を推進している方々などには、そういう役割も期待しています。興味を持つアーティストさんには養成講座を受けてもらって、実際にワークショップを体験してもらう仕組みができれば、その壁はそんなに高いものではないと思ってます。
 「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)
「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)
 「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)
「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)
唐川 ワークショップの実践をまとめた冊子『ザンネンなわたしたちの世界を変える6つの試み』に、職員さん、メンバーさん、アーティストさんにヒアリングして、共通項を見つけてから企画をつくると紹介されていらっしゃいましたよね。そういう創作現場であればどんな人でも参加しやすくなるのではないかと思いました。私もこれまでの企画の中で、アーティストはアーティストとして、現場の人は現場の人としていつも通り活動してもらう中で何が生まれるかを模索しています。福祉現場でのワークショップとなると、アーティスト側も「何か役に立たなければ」というマインドが出てきてしまう。実際に、最近はアーティストが福祉現場、教育現場に入ることも増えていて、そういう場が増えればお金にもなるし生活もできるようになるかもしれない。けれど、「もともとコミュニケーション能力がないから自分には無理」というアーティストもいるはずなんです。私の考えでは、コミュニケーションができなくても、ただそこでひたすら版画を刷っている姿を見せるだけでも、パフォーマンスとして日常を変えるきっかけになると思います。重要なのは、その場に関わる人たちが何を持っていて、何がしたいのか、一人ではなかなか表現できないものをどうやったらみんなで実現できるかを共に考えることかなと。
 交換留藝(野口桃江さん)。ロッヂに通っている方から信州に伝わる歌を習う
交換留藝(野口桃江さん)。ロッヂに通っている方から信州に伝わる歌を習う
 交換留藝(野口桃江さん)。夏休みの子ども向けのワークショップを実施
交換留藝(野口桃江さん)。夏休みの子ども向けのワークショップを実施
鈴木 本当にそうです。アーティストこそマイノリティですから。現代社会は生きづらいかもしれないけど、ワークショップはそれをひっくり返していこうという試み。だから共闘できるんです。「まどか工房」に入った白神ももこさんは今や「キラリふじみ」(富士見市民文化会館)の芸術監督ですけど、僕が彼女の作品を初めて見たときは、ダンスなのに舞台上でバレエに対する怨嗟をずっとしゃべってた。つまりファインアートのど真ん中を行けなかった恨みつらみから創作しているかのように見えました。でもそこから新たな展開を経て、今や子どもから高齢者まで地域でアートを使ったかかわりをつくっている。根っこにマイノリティとしての自覚があるアーティストと、障害がある人たちとの出会いには可能性があると思うんです。彼女らは非主流という意味で同じような扱いを受けてきている。白神さんもそれをしたたかにひっくり返してきた。障害のある人も「2軍」や「補欠」扱いで社会にいさせてもらってるわけではなくて、むしろ「こっちにこそすごさがあるだろう?」くらいのつもりで社会ごとひっくり返していきたい。単なるお教室じゃないワークショップでアートの力を使って一人ひとりをちゃんと肯定していく先にそんなことも可能になるんじゃないかと思っています。
マイノリティと言われるもの同士がタッグを組んで社会の価値観をひっくり返すというのはとても重要なことですよね。
鈴木 実は私も人とかかわれない人間だったけれど、本当に現場で変えてもらったんですよ。もちろん人とかかわれば嫌なことも面倒なことも起こるけども、その先がある。そう思えるようになったのはこの場があったからだと思います。芸術だけじゃなくて、日常のすべてが表現なんだということに改めて気づかせてももらった。極端なことを言うと、障害がある人たちは社会では役に立たないと見なされたり、表現も往々にして問題行動だとか言われちゃったり、厄介者として捉えられかねない。でもその余計と思われている部分に人間としての豊かさがあるのに、本当に「問題」を起こさないように見張って先回りして表現をつぶしていくことがケアの仕事だって勘違いされてしまうのは残念すぎる。この社会に「余計」とされる部分の豊かさを価値として認め、「この部分があってこそ、この人だよ」ということを世に知らしめていくというか、周りの人とつないでいくのが僕らの仕事なんですよね。その仕事を見えなくさせているのことこそが社会の問題ですね。
唐川 それこそ福祉はウェルビーイングのことですけれど、社会全体がウェルビーイングであるために、個々人の必要最小限のニーズだけにフォーカスしていればいいという考えは真逆をいっていますよね。
鈴木 そう、マジョリティの都合ですよ。「より効率が良い」とか「生産性が高い」とか、この社会で良いとされている価値観を守りたいんでしょうけど、それはマジョリティにとっても本当にそこまで「良い」ものなのかという話になると思う。これだけ自死が多い社会は何か問題があるはず。それは「良い」としている指標自体が狭すぎたり、どこか間違っているから、こんなにもしんどい人が多いのかもしれない。その被害をわかりやすく被っているのが障害のある人たちなんです。何かが違うってだけで生きづらさを抱えてしまう社会や、苦しめてくる因習なんかをぶち壊し、価値観を広げていくことで、実はマジョリティだと思っている人たちの生きづらさも減っていく、そっちの方に向かわないと社会はどんどん息苦しくなると思う。
唐川 アーティストをはじめ多様な人がケアの現場に混ざってくると、知識を持っていないからこそ、ケアの観点からするともしかしたら良くないこともやっちゃう。そしてそれがとても大事なことかなと思います。
 スクショツーショット
スクショツーショット
鈴木さんは今後、どういうふうに動いていかれるんですか?
鈴木 カプカプは「アート系施設」ではないと言い続けていますが、アート系のトップランナーは必要だと思っています。いろいろなものを切り拓いて可能性を広げていくことは大切です。ただそれを見学した人が「うちにはできない」と落胆してしまう現状もある。それはそうですよ。そのことに特化してずっとやっているのだし、アートのためのスタッフも集めているわけですから。そんなふうにトップランナーだけがアートに特化するやり方ではアートを取り入れる施設の数は増えない。生活介護事業所だけでも日本に1万、就労系も含めれば2万以上あるんです。その福祉施設に税金が投入されていることはすごく大きなこと。各所にある数千万円規模の予算の一部を、アートによって障害福祉施設の日常を豊かにすること、すなわちアーティストによるワークショップに使おうという流れをつくりたいと考えています。実は今回のワークショップ企画を各所で実施するのにかかるのは、年間予算の1~2%に過ぎません。ギリギリで運営していてその1~2%も出せないなんて言われるかもしれませんが、アートを取り入れて環境を整えていくことで、メンバーさんがもっと通いたくなる施設になっていけば、回収するのも難しくないはずです。やらない言い訳をさせないくらいに、魅力的なお誘いをできるようになって、いずれこのワークショップを全国に広めていきたいと思ってます。
日本の旧態依然の福祉の中で障害がある人たちは、ずっと「個々人に問題があり、それを社会に適応できるように指導してあげなくてはならない」というような扱いを受けています。「問題ではなく課題と呼ぼう」みたいに、表面的には差別的な言動はされなくなっているけれども、根底にある価値観は変わってない。その状況を壊すためにも遊びの部分、余計だと思われてる部分こそ、人間の大切なものなんだとちゃんと見えるようにしていく。そのときにアーティストの視点は欠かせないと思っています。ワークショップを通して、問題は個人ではなくて社会やわたしたちの価値観にこそあることに、まずは障害福祉に従事する人たちが気づいていく。ワークショップを広める過程で、つまらない施設が減って、否定される人が一人でも減ればいい。さらに障害福祉から新しい価値観が社会に広がっていき、世の中の生きづらい人が減っていくことこそ、僕らが税金でやってる意味かなと思ってます。